Tendo
Vintage Low Chair
今日も今日とて暑いですが、連日の35度越えを考えれば幾分過ごしやすいお日柄となっています。皆様いかがお過ごしでしょうか。
日本の夏は暑い。アフリカや中央アジアの方が気温的には高いはずですが、温度と湿度がタッグを組んだ日本の夏はやはり嫌な意味でスペシャルです。
所が変われば暮らし方が異なり、それに用いるインテリアであっても少しずつ様相が変わってきます。
そんな、「日本らしさ」が存分に楽しめるデザイナーズプロダクトが入荷致しましたので、是非ご紹介させてください。
心を空気に解き放つ
 >>この商品の詳細を確認する
>>この商品の詳細を確認する
日本は森の国。身の回りにあって強度があり、加工しやすい。そして何より温もりがある木を用いた家具は日本において多く作られてきました。
豊富で良質な素材を生かした旭川家具。婚礼家具にはじまり、今ではチェストなどの箱ものをはじめ優れたデザインを多く発表する大川家具。そして古くは万葉集までその存在が確認できる確かな技術が生きる飛騨家具等々。
資源と技術、そして運搬などの複数の要件が揃った場所は家具の名産地として栄えていますが、今回のブランドほどその地域を代表しているところはないのでしょうか。

その名は天童木工(てんどうもっこう)。1940年山形県は天童市に、大工や建具、指物などの木工職人が集い立ち上がった組合が元になって生まれた企業です。
戦中は弾薬箱やおとりにするための木製飛行機などを製造していましたが、戦後復興と共に拡大する需要に応えるようにその規模を大きくしています。


契機となったのは今や世界をリードするといっても過言ではない、成型合板技術。
技術部長を務め、また優れたアイテムを自身でも設計した乾三郎が電子レンジを応用した装置を取り入れていったことで、軽くて丈夫、そして新たな造形が生まれるプライウッド(成型合板)。
その新素材は新たな価値を模索するデザイナー達の感性を刺激し、ジャパニーズミッドセンチュリ―と呼ばれる魅力的なアイテムが天童木工から多く発表されました。


社内からは先述の乾三郎、菅沢光政、社長を歴任した加藤徳吉等のほか、柳宗理、剣持勇、丹下健三、豊口克平、松村勝男、水之江忠臣ら。(※敬称略)
プライウッドの可能性を求め開催した自社のコンペティションによって田辺麗子、ヤマナカグループなど、そして海外からもブルーノ・マットソンやシャルロット・ペリアンと協働したデザイナーを挙げればきりがありません。
しかもそれはミッドセンチュリーからあとも続き、今も新しいデザインプロダクトが世に出されているのです。

その輝かしい足跡の中のひとつが、今回の低座椅子。
デザインを手掛けたのは長大作。名建築を多く手掛けた坂倉準三のもとで勤務した経験を持ち、1958年に手掛けた松本幸四郎邸において生み出された1脚です。


全体から漂うのは「和」の雰囲気。
フレームは、東京文化会館に残る音響板のようにどこか彫刻のような印象。そのフレーム以外に見える直線はほとんどなく、折り返しも柔らかな丸みを帯びています。

松本幸四郎は歌舞伎の大家。もちろん日本の文化の粋を集めた邸宅であり、畳の部屋も多く存在します。
フレームがソリのように真っすぐ伸びる「畳摺り」は4つの点で接地する通常の椅子と異なり畳にも優しく使いやすいように考えられた形。
高さが約65センチ、座面高が約28センチとラウンジチェアとしても低めの部類になるのも、畳からも移りやすく、視点を大きく変えないように意識されているためだと思われます。

参考として並べてみましたが、なんとも贅沢な画。
そう、そして写真の通り現在経堂店には
2点の低座椅子が入荷しているのです。(イームズの
LCWもあります!)
やはり人気のある椅子なので現在でも製造は続けられているのですが、その場合フレームはナラ(オーク材)。
上質な赤みがなんともレトロなチーク材は、伐採が制限されて廃番仕様となってからは製造されていないのです。


ビンテージでしか手に入らない仕様となればその状態が気になるところですが、今回は2脚ともウレタンを交換しファブリックは張替え済み。
前回ご紹介したネイビー系はリバコ社のNC、そして今回のライトブルーはマハラム社のモードという信頼性の高い生地を専門業者にてしつらえてあります。
平織りの生地はさっぱりとした質感で肌触りも良く、低座椅子のフォルムの良さを引き立てます。
個人的にNC生地は国産だけあって、ほのかな白さの光沢が「和」の雰囲気と相性が良く、マハラムはより細かな織目と発色の良さで上品さが増している印象です。
レトロモダンならNC、チーク×ライトブルーという北欧モダン好きならマハラムの1脚をお勧めしたいと思います。悩ましいけれど、選ぶのが楽しいヤツですねこれは。


わしづかみにできる程の分厚いウレタンクッションは見ただけで座ってみたくなる、そんな居心地の良さを想像させてくれます。
時は1958年、まだまだ和室での暮らしが一般的な家屋において、西洋文化による洗練と今までの畳暮らしのあり方がせめぎ合っていた瞬間。
市井の人々から尊敬される松本家において、その両方を選択できるように長大作が考え尽くした形が今こうして残っています。


西洋椅子ならあぐらはかけない。畳なら背もたれに身体を預けて、西洋人のように背筋を伸ばして寛げない。
2023年、洋家具での暮らしが根付いた今は、手放さなかった日本の美意識が残る貴重な1脚になっています。
低めの視点から、高くなったお部屋の天井を見上げれば。自分の中にある日本のエッセンスが、蘇ってくるような気がします。

美しいもので寛ぐ悦びを、当時物のスペシャルなアイテムで。評価が高まるジャパニーズモダンのビンテージは次の入荷がいつになるのかは分かりません。
選べるうちに、是非とっておきの1脚をお迎えくださいませ。

 >>この商品の詳細を確認する
日本は森の国。身の回りにあって強度があり、加工しやすい。そして何より温もりがある木を用いた家具は日本において多く作られてきました。
豊富で良質な素材を生かした旭川家具。婚礼家具にはじまり、今ではチェストなどの箱ものをはじめ優れたデザインを多く発表する大川家具。そして古くは万葉集までその存在が確認できる確かな技術が生きる飛騨家具等々。
資源と技術、そして運搬などの複数の要件が揃った場所は家具の名産地として栄えていますが、今回のブランドほどその地域を代表しているところはないのでしょうか。
>>この商品の詳細を確認する
日本は森の国。身の回りにあって強度があり、加工しやすい。そして何より温もりがある木を用いた家具は日本において多く作られてきました。
豊富で良質な素材を生かした旭川家具。婚礼家具にはじまり、今ではチェストなどの箱ものをはじめ優れたデザインを多く発表する大川家具。そして古くは万葉集までその存在が確認できる確かな技術が生きる飛騨家具等々。
資源と技術、そして運搬などの複数の要件が揃った場所は家具の名産地として栄えていますが、今回のブランドほどその地域を代表しているところはないのでしょうか。
 その名は天童木工(てんどうもっこう)。1940年山形県は天童市に、大工や建具、指物などの木工職人が集い立ち上がった組合が元になって生まれた企業です。
戦中は弾薬箱やおとりにするための木製飛行機などを製造していましたが、戦後復興と共に拡大する需要に応えるようにその規模を大きくしています。
その名は天童木工(てんどうもっこう)。1940年山形県は天童市に、大工や建具、指物などの木工職人が集い立ち上がった組合が元になって生まれた企業です。
戦中は弾薬箱やおとりにするための木製飛行機などを製造していましたが、戦後復興と共に拡大する需要に応えるようにその規模を大きくしています。

 契機となったのは今や世界をリードするといっても過言ではない、成型合板技術。
技術部長を務め、また優れたアイテムを自身でも設計した乾三郎が電子レンジを応用した装置を取り入れていったことで、軽くて丈夫、そして新たな造形が生まれるプライウッド(成型合板)。
その新素材は新たな価値を模索するデザイナー達の感性を刺激し、ジャパニーズミッドセンチュリ―と呼ばれる魅力的なアイテムが天童木工から多く発表されました。
契機となったのは今や世界をリードするといっても過言ではない、成型合板技術。
技術部長を務め、また優れたアイテムを自身でも設計した乾三郎が電子レンジを応用した装置を取り入れていったことで、軽くて丈夫、そして新たな造形が生まれるプライウッド(成型合板)。
その新素材は新たな価値を模索するデザイナー達の感性を刺激し、ジャパニーズミッドセンチュリ―と呼ばれる魅力的なアイテムが天童木工から多く発表されました。

 社内からは先述の乾三郎、菅沢光政、社長を歴任した加藤徳吉等のほか、柳宗理、剣持勇、丹下健三、豊口克平、松村勝男、水之江忠臣ら。(※敬称略)
プライウッドの可能性を求め開催した自社のコンペティションによって田辺麗子、ヤマナカグループなど、そして海外からもブルーノ・マットソンやシャルロット・ペリアンと協働したデザイナーを挙げればきりがありません。
しかもそれはミッドセンチュリーからあとも続き、今も新しいデザインプロダクトが世に出されているのです。
社内からは先述の乾三郎、菅沢光政、社長を歴任した加藤徳吉等のほか、柳宗理、剣持勇、丹下健三、豊口克平、松村勝男、水之江忠臣ら。(※敬称略)
プライウッドの可能性を求め開催した自社のコンペティションによって田辺麗子、ヤマナカグループなど、そして海外からもブルーノ・マットソンやシャルロット・ペリアンと協働したデザイナーを挙げればきりがありません。
しかもそれはミッドセンチュリーからあとも続き、今も新しいデザインプロダクトが世に出されているのです。
 その輝かしい足跡の中のひとつが、今回の低座椅子。
デザインを手掛けたのは長大作。名建築を多く手掛けた坂倉準三のもとで勤務した経験を持ち、1958年に手掛けた松本幸四郎邸において生み出された1脚です。
その輝かしい足跡の中のひとつが、今回の低座椅子。
デザインを手掛けたのは長大作。名建築を多く手掛けた坂倉準三のもとで勤務した経験を持ち、1958年に手掛けた松本幸四郎邸において生み出された1脚です。

 全体から漂うのは「和」の雰囲気。
フレームは、東京文化会館に残る音響板のようにどこか彫刻のような印象。そのフレーム以外に見える直線はほとんどなく、折り返しも柔らかな丸みを帯びています。
全体から漂うのは「和」の雰囲気。
フレームは、東京文化会館に残る音響板のようにどこか彫刻のような印象。そのフレーム以外に見える直線はほとんどなく、折り返しも柔らかな丸みを帯びています。
 松本幸四郎は歌舞伎の大家。もちろん日本の文化の粋を集めた邸宅であり、畳の部屋も多く存在します。
フレームがソリのように真っすぐ伸びる「畳摺り」は4つの点で接地する通常の椅子と異なり畳にも優しく使いやすいように考えられた形。
高さが約65センチ、座面高が約28センチとラウンジチェアとしても低めの部類になるのも、畳からも移りやすく、視点を大きく変えないように意識されているためだと思われます。
松本幸四郎は歌舞伎の大家。もちろん日本の文化の粋を集めた邸宅であり、畳の部屋も多く存在します。
フレームがソリのように真っすぐ伸びる「畳摺り」は4つの点で接地する通常の椅子と異なり畳にも優しく使いやすいように考えられた形。
高さが約65センチ、座面高が約28センチとラウンジチェアとしても低めの部類になるのも、畳からも移りやすく、視点を大きく変えないように意識されているためだと思われます。
 参考として並べてみましたが、なんとも贅沢な画。
そう、そして写真の通り現在経堂店には2点の低座椅子が入荷しているのです。(イームズのLCWもあります!)
やはり人気のある椅子なので現在でも製造は続けられているのですが、その場合フレームはナラ(オーク材)。
上質な赤みがなんともレトロなチーク材は、伐採が制限されて廃番仕様となってからは製造されていないのです。
参考として並べてみましたが、なんとも贅沢な画。
そう、そして写真の通り現在経堂店には2点の低座椅子が入荷しているのです。(イームズのLCWもあります!)
やはり人気のある椅子なので現在でも製造は続けられているのですが、その場合フレームはナラ(オーク材)。
上質な赤みがなんともレトロなチーク材は、伐採が制限されて廃番仕様となってからは製造されていないのです。

 ビンテージでしか手に入らない仕様となればその状態が気になるところですが、今回は2脚ともウレタンを交換しファブリックは張替え済み。
前回ご紹介したネイビー系はリバコ社のNC、そして今回のライトブルーはマハラム社のモードという信頼性の高い生地を専門業者にてしつらえてあります。
平織りの生地はさっぱりとした質感で肌触りも良く、低座椅子のフォルムの良さを引き立てます。
個人的にNC生地は国産だけあって、ほのかな白さの光沢が「和」の雰囲気と相性が良く、マハラムはより細かな織目と発色の良さで上品さが増している印象です。
レトロモダンならNC、チーク×ライトブルーという北欧モダン好きならマハラムの1脚をお勧めしたいと思います。悩ましいけれど、選ぶのが楽しいヤツですねこれは。
ビンテージでしか手に入らない仕様となればその状態が気になるところですが、今回は2脚ともウレタンを交換しファブリックは張替え済み。
前回ご紹介したネイビー系はリバコ社のNC、そして今回のライトブルーはマハラム社のモードという信頼性の高い生地を専門業者にてしつらえてあります。
平織りの生地はさっぱりとした質感で肌触りも良く、低座椅子のフォルムの良さを引き立てます。
個人的にNC生地は国産だけあって、ほのかな白さの光沢が「和」の雰囲気と相性が良く、マハラムはより細かな織目と発色の良さで上品さが増している印象です。
レトロモダンならNC、チーク×ライトブルーという北欧モダン好きならマハラムの1脚をお勧めしたいと思います。悩ましいけれど、選ぶのが楽しいヤツですねこれは。

 わしづかみにできる程の分厚いウレタンクッションは見ただけで座ってみたくなる、そんな居心地の良さを想像させてくれます。
時は1958年、まだまだ和室での暮らしが一般的な家屋において、西洋文化による洗練と今までの畳暮らしのあり方がせめぎ合っていた瞬間。
市井の人々から尊敬される松本家において、その両方を選択できるように長大作が考え尽くした形が今こうして残っています。
わしづかみにできる程の分厚いウレタンクッションは見ただけで座ってみたくなる、そんな居心地の良さを想像させてくれます。
時は1958年、まだまだ和室での暮らしが一般的な家屋において、西洋文化による洗練と今までの畳暮らしのあり方がせめぎ合っていた瞬間。
市井の人々から尊敬される松本家において、その両方を選択できるように長大作が考え尽くした形が今こうして残っています。

 西洋椅子ならあぐらはかけない。畳なら背もたれに身体を預けて、西洋人のように背筋を伸ばして寛げない。
2023年、洋家具での暮らしが根付いた今は、手放さなかった日本の美意識が残る貴重な1脚になっています。
低めの視点から、高くなったお部屋の天井を見上げれば。自分の中にある日本のエッセンスが、蘇ってくるような気がします。
西洋椅子ならあぐらはかけない。畳なら背もたれに身体を預けて、西洋人のように背筋を伸ばして寛げない。
2023年、洋家具での暮らしが根付いた今は、手放さなかった日本の美意識が残る貴重な1脚になっています。
低めの視点から、高くなったお部屋の天井を見上げれば。自分の中にある日本のエッセンスが、蘇ってくるような気がします。
 美しいもので寛ぐ悦びを、当時物のスペシャルなアイテムで。評価が高まるジャパニーズモダンのビンテージは次の入荷がいつになるのかは分かりません。
選べるうちに、是非とっておきの1脚をお迎えくださいませ。
美しいもので寛ぐ悦びを、当時物のスペシャルなアイテムで。評価が高まるジャパニーズモダンのビンテージは次の入荷がいつになるのかは分かりません。
選べるうちに、是非とっておきの1脚をお迎えくださいませ。






















 美しい北欧の名品
美しい北欧の名品 曲線が魅せる美しい曲木
曲線が魅せる美しい曲木 時代を表現したポストモダン
時代を表現したポストモダン 感性を刺激するデザイナーズ
感性を刺激するデザイナーズ 想いを馳せたスペースエイジ
想いを馳せたスペースエイジ 魅力が詰まったレトロポップ
魅力が詰まったレトロポップ 日本の民芸アイテム
日本の民芸アイテム やすらぎを感じるクラフト家具
やすらぎを感じるクラフト家具 ヴィンテージ家具の商品一覧へ
ヴィンテージ家具の商品一覧へ 日本のヴィンテージ
日本のヴィンテージ 米国のヴィンテージ
米国のヴィンテージ 北欧のヴィンテージ
北欧のヴィンテージ 西欧のヴィンテージ家具
西欧のヴィンテージ家具 西欧のアンティーク家具
西欧のアンティーク家具 各国のヴィンテージ家具
各国のヴィンテージ家具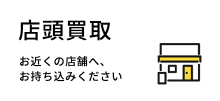








 商品保管サービスについて
商品保管サービスについて
















